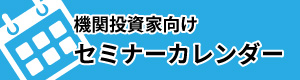連載 小倉邦彦の資産運用時事コラム第7回 特別編「企業年金の先輩に聞く資産運用の過去・現在・未来」~元DIC企業年金基金 理事 近藤英男氏ロングインタビュー~【後編】
年金基金の資産運用に大きな足跡を残された近藤英男氏(元DIC企業年金基金理事)へのロングインタビュー。「前編」「中編」に続き、今回は、現在の市場環境下での諸課題に対する考えや、企業年金連絡協議会 資産運用研究会の活動を中心にお話を聞きました。
「中編」の記事はこちら。
(目次)
1.はじめに
2.年金基金時代の基本的な運用方針
3.運用会社との付き合い方
4.母体企業との付き合い方
5.PA投資について ~ なぜ2004年から始めたのか?
6.PA投資について ~ なぜリーマンショック後に拡大したのか?
7.PA投資について ~ 各資産クラスに対する考え方(投資スタンス)
8.流動性のあるオルタナティブ投資(ヘッジファンド、マルチアセット等)への対応
9.伝統四資産への対応
【後編】
10.最近の運用環境(2つのトピックス:難しい債券運用とPA投資の拡大)に対する考え
11.企業年金連絡協議会 資産運用研究会について
10.最近の運用環境(2つのトピックス:難しい債券運用とPA投資の拡大)に対する考え
小倉 最近の運用を取り巻く環境で、多くの企業年金が頭を悩ませているのが債券運用だと思います。債券運用のコアであったヘッジ外債は、2022年度は日本を除く先進国で金融政策の正常化が進み、長期金利上昇でこれまで経験したことがないような大きなキャピタルロスが発生しました。今年度は長期金利の上昇はある程度収まってきているようですが、日米金利差の拡大によるドル円ヘッジコストの上昇や、逆イールドによりヘッジ外債のキャリーは大きなマイナスに落ち込んでいます。為替ヘッジを外す動きも一部ではありますが、足元のドル円相場の水準を考えると円高方向に動くリスクもあり躊躇されるところです。円債は順イールドでキャリーもプラスですが、日銀の金融政策見直しによっては長期金利が上昇するリスクもあり避難場所として円債を選択するというのもなかなか難しいところです。近藤様が基金の運用執行理事であれば債券運用についてはどのように対応されていたでしょうか。
ピックアップ
よく見られている記事ランキング
-
連載 小倉邦彦の資産運用時事コラム第17回 大和ファンド・コンサルティング 今福リサーチフェローとプライベートアセット投資を徹底討論 【前編】
Web限定 プライベートアセット 寄稿 資産運用時事コラム -
オルインセミナーレポート 「金融政策の転換と為替市場の見通し ―日本は円安を止めることができるのか」
セミナーレポート 市場見通し -
野村年金ニュース解説企業年金の運用状況(2024年度第1四半期)
Web限定 企業年金 -
オルインセミナーレポート 「多様な分散がもたらす頑健なポートフォリオ構築のポイントは」
オルタナティブ セミナーレポート 企業年金 -
オルインセミナーレポート 「市場環境の変化に対応するポートフォリオ運用の考え方」
Web限定 オルタナティブ セミナーレポート プライベートアセット 債券 -
アライアンス・バーンスタインの運用責任者に聞く 銀行の自己資本強化で脚光浴びるプライベートデットの現在
Web限定 プライベートデット 市場見通し -
連載 小倉邦彦の資産運用時事コラム第9回 フォローの風に乗るプライベートデットの最新動向を探る後編:ダイレクトレンディングに関する井戸端会議 ~ 最新動向を議論する
Web限定 寄稿 資産運用時事コラム -
「Tokyo Asset Management Forum2022 Autumn」
開催レポート
運用会社の多様化でアセットオーナーの運用高度化を後押しするWeb限定 セミナーレポート -
注目を集める不動産新セクター、トリプルネットリース
Web限定 不動産 企業年金 金融法人 -
地域金融機関から注目集める新ソリューション「OCIO」とは何か?
Web限定 金融法人