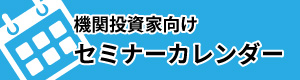ご存じのように投資運用の世界の人気や評価は移ろいやすく、今は飛ぶ鳥を落とす勢い勢いの投資ファンド・戦略であっても、いつかは厳しい状況に直面してしまう例は、枚挙にいとまがありません。ひとたび旗色が悪くなるや、そのような投資ファンド・戦略は真っ先に生贄にされます。
特にそれが顕著であったのが、2008年の世界金融危機時です。ヘッジファンド、不動産、プライベート・エクイティといった「オルタナティブ」運用は、諸悪の根源的扱いをされ、「オルタナティブ商品に投資しなければ、これほどの損失は被らなかった」という類の後知恵の批判に対応を迫られた投資家も多かったのです。
しかしながら、危機から10年以上の時が経ちはっきりしていることは、しっかりとした投資の枠組みを踏まえた「オルタナティブ」投資は、大きな成果をもたらしたということです。そして、株式や債券といった伝統的資産クラスだけで、従来と同じようなやり方での運用だけでは、資産運用のプロ・責任者に要求・期待されるリターンの達成は難しいということです。
原書の初代”Pioneering Portfolio Management”の訳本が2003年に出版されてから、早17年が過ぎました。振り返ってみれば、その頃既に相当低かった金利も、2008年の金融危機を経て、主要国におけるQEによって一段と低下し、リターンを求めてグローバルに資金が駆け巡り、年を経るごとに運用難が合言葉のように交わされ、投資対象となる資産も拡大、複雑化の一途を辿ってきました。
一方で当訳本は出版当時、異なるアセット・オーナーが結集して翻訳した初めての本として、当時、注目を浴びた面もありましたが、初代の翻訳作業を担った面々も、そのほとんどが当時属していた組織から別の組織へと移ってしまいました。
今回この全面改訂・拡大版の翻訳のお話しをパンローリング株式会社から伺い、翻訳作業の大変さを思い起こし一時迷ったものの、やはりこの仕事は自分達でやり遂げたいとの思いから、前回の翻訳事務局のメンバーで訳者チームを結成し、改めてゼロからのスタートで翻訳作業に臨みました。
当然ですが、メンバーそれぞれの立場でいろいろな経験を踏まえ、初代の翻訳を行っていた当時とは比較にならないほどの経験を経た上での改訂版翻訳作業となりました。そこで、18年経った今も改めて、いや一層痛感したことは、この本は年を経ても色褪せることのない、次世代に残すべき、運用に携わる上で哲学的な本であるということです。
そうした信念を深めた大きな理由の一つは、著者である米国イェール大学寄贈基金のCIOであるデビッド・F・スウェンセンがこの本で伝えようとしたことが、運用、投資に関するいわゆる“How To”や“Know How”ではなく、“Know Why” だからです。機関投資家の投資や運用においては、先ずは、何らかの目的で制度(例えば寄贈基金や企業年金、あるいは金融機関における投資枠など)が設けられ、その制度の有する目的を達成するために、投資、運用が始まるわけです。従って、投資、運用の担当者は、その上位目的の達成に貢献する投資・運用を厳選するという作業を担うことになります。
その際、本来的に担当者に求められるものは、その資産クラスや投資戦略での資産運用を、「どうやる(How)」のかでだけはなく、「なぜやる(Why)」のかを考えることができる資質です。後者が欠如していると、他の組織がやっていること、今流行っていること、評価が高いからということを、「どうやる(How)」か、いかに上手くやるかに、ただ傾注する「真面目なchaser」になってしまいがちになることを、初回翻訳後から今日に至るまで、数多く見てきました。そして、このような投資行動を行ったとき、その帰結は明らかです。低い投資成果です。
確かにこの全面改訂版では、新しい投資対象の資産クラスや投資戦略が加えられています。しかしながら、著者の意図は、それが時流だから「どうやる(How)」かについて述べることにはありません。あくまで、新しい「素材」に出会ったとき、「なぜやる(Why)」のか考える、その思考の道筋を示すことにあるのです。
従って、初版翻訳時よりも新しい投資対象(資産クラス・投資戦略)がはるかに増え、実際に投資も行われている現在、またこれからもその傾向は続くであろうと容易に予想される将来を考えると、わが国の投資、運用の任に当たる担当者、上席者、また、理事会、各種委員会の監督者にとって、この本の必要性は初版翻訳時よりも増していると拝察されます。この本を貫く著者の揺らぐことのない信念こそが、この本を”Classic”、あるいは“Modern”と呼ばせない“Current”なものにしているのです。
繰り返しになりますが、この後10年も経てば、この世界から退出することが明らかな私たち、横並び金利、規制でがんじがらめの世界から、バブル、規制緩和、バブル崩壊、グローバル化、金融危機、AIを含めたテクノロジーの急速な発展、ゼロ金利と大きな環境変化を経験し、構造変化に直面してきた5・3・3・2世代の私たちは、この資産運用の古典ともいうべき翻訳本を手に取っていただけた次世代の方々に対して、少しでも何かを残すことができるのではと確信している次第です。
訳者チーム一同 2021年3月
ピックアップ
よく見られている記事ランキング
-
連載 小倉邦彦の資産運用時事コラム第17回 大和ファンド・コンサルティング 今福リサーチフェローとプライベートアセット投資を徹底討論 【前編】
Web限定 プライベートアセット 寄稿 資産運用時事コラム -
オルインセミナーレポート 「金融政策の転換と為替市場の見通し ―日本は円安を止めることができるのか」
セミナーレポート 市場見通し -
野村年金ニュース解説企業年金の運用状況(2024年度第1四半期)
Web限定 企業年金 -
オルインセミナーレポート 「多様な分散がもたらす頑健なポートフォリオ構築のポイントは」
オルタナティブ セミナーレポート 企業年金 -
オルインセミナーレポート 「市場環境の変化に対応するポートフォリオ運用の考え方」
Web限定 オルタナティブ セミナーレポート プライベートアセット 債券 -
アライアンス・バーンスタインの運用責任者に聞く 銀行の自己資本強化で脚光浴びるプライベートデットの現在
Web限定 プライベートデット 市場見通し -
連載 小倉邦彦の資産運用時事コラム第9回 フォローの風に乗るプライベートデットの最新動向を探る後編:ダイレクトレンディングに関する井戸端会議 ~ 最新動向を議論する
Web限定 寄稿 資産運用時事コラム -
「Tokyo Asset Management Forum2022 Autumn」
開催レポート
運用会社の多様化でアセットオーナーの運用高度化を後押しするWeb限定 セミナーレポート -
注目を集める不動産新セクター、トリプルネットリース
Web限定 不動産 企業年金 金融法人 -
地域金融機関から注目集める新ソリューション「OCIO」とは何か?
Web限定 金融法人