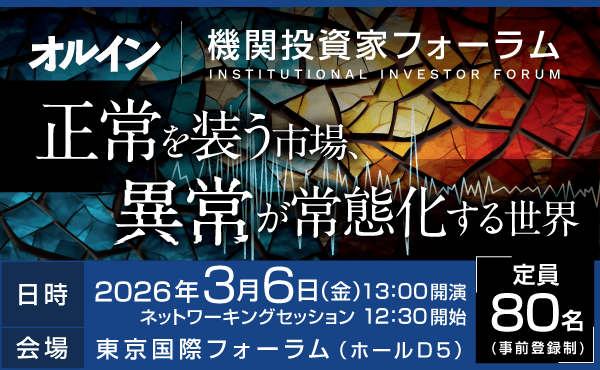欧州で浸透するESG投資だが、米国トランプ政権の誕生によってにわかに風向きが変わりつつあるのは周知のとおりだ。そうした中でも、中長期で見ればESG投資の推進は避けて通れないと考える資産運用業界関係者は少なくない。その一人が、BNPパリバ・アセットマネジメントのグローバル・ヘッド・オブ・スチュワードシップ&議決権行使を務めるマイケル・ハースコビッチ氏だ。ESG投資の最前線ではどのような議論が行われ、日本の市場はどう評価されているのか――。「国際コーポレートガバナンスネットワーク(ICGN)」の副議長でもある同氏に話を聞いた。

BNPパリバ・アセットマネジメント
グローバル・ヘッド・オブ・スチュワードシップ&議決権行使
マイケル・ハースコビッチ 氏(Michael Herskovich)
ESGにおける日本企業の評価とトランプ政権の影響
――3月4日・5日に東京で行われた「ICGN 30周年アジア会議」に副議長として参加されました。参加者の間では特にどのような話題に関心が寄せられていましたか?
今回のイベントでは、ボードミーティング、全体会議、政策提唱という3つの構成で話し合いが行われました。米国、欧州、アジア、オーストラリアなどさまざまな地域の情報交換が目的でしたが、日本に関するパネルディスカッションでは株主の権利について議論し、日本企業のサステナビリティ面での進化が評価されていました。
特に焦点を当てられたのは、取締役会に関するガバナンスで、社外取締役の独立性や人材の多様性、なかでも女性取締役の割合などです。まだ改善の余地はありますが、日本企業がこれらの課題に取り組む社会的意義に気づき、行動しようとしていることが確認できました。こうしたことから、日本市場におけるESGについて、欧米と比べればまだ足りない部分もあるものの、現状の変化に対してはポジティブに捉えています。
――米国トランプ大統領就任によって、脱炭素やダイバーシティの動きに逆風が吹くとの見方がありますが、ご意見をお聞かせください。
ESGに関するトランプ政権の影響は、米国と欧州で異なります。欧州ではネットゼロ(温暖化ガスの実質排出ゼロ)の最終的なゴールは変わっておらず、それに沿った方向にルール整備が進んでいます。また、そもそも政治が変わったからといって、私たちの基本的な考え方が変わるものではありません。
私たちは、長期にわたって運用パフォーマンスを追求するために、ESGを組み入れた投資が不可欠だと考えています。短期的な収益を追うだけでは長期パフォーマンスは達成できません。そもそも、地球環境が持続可能でなければ、企業が長期パフォーマンスを実現すること自体も不可能でしょう。良いガバナンスや取締役の多様性は、企業価値向上につながると確信しています。
もちろん、ESGは、国や地域によって用語や定義、法律など異なる点は多々あります。しかし、企業活動の根本にESGの考え方がなければ、企業価値の追求や長期パフォーマンスの向上は成し得ません。各国のローカルな考え方に合わせつつ、気候変動などのリスク管理とパフォーマンス向上の両面から投資家として行動することが重要だと考えています。
企業価値を追求し、何が投資家のリスクになっていて、どうすればリターンを高められるのかを分析・実行する。投資をめぐる環境は常に変化し続けていますが、長期的な目で見て私たちのすべきことは変わっていません。
「3つのE」戦略
――BNPパリバAMがサステナビリティ投資を行ううえで重要視されている「3つのE」について、具体的に教えてください。
当社では、サステナビリティを実現するために、「エネルギー転換(Energy transition)」、「健全な生態系(healthy Ecosystems)」、「社会における平等性の向上(greater Equality)」の「3つのE」に焦点を当てています。投資アプローチ、スチュワードシップ活動、運用商品、当社自身のCSR方針といったさまざまな観点から、取り組みを展開中です。
「3つのE」を設定したのは、これらが企業の長期的な成長ドライバーとなるからです。例えば、エネルギー転換では脱炭素の観点で企業がどう成長していくのか、健全な生態系では自然の破壊をどう防ぐのか、社会における平等性の向上では取締役の多様性をどう実現するのか。こうした点から企業の成長が期待できます。
――「3つのE」実現に向け、どのように取り組みを進めていますか?
「3つのE」のそれぞれの実現に向けて、3つのロードマップを策定しました。
エネルギー転換では、「ネットゼロ・ロードマップ」を策定し、10のカテゴリーに対するコミットメントを発表しました。その内の一つでは、2050年ネットゼロに向けた企業の進捗を「Achieved(ほぼ達成)」「Aligned(整合済み)」「Aligning(整合途上)」「整合せず」の4段階で評価。上位3つの評価を獲得した企業への投資割合を2030年までに60%まで引き上げるという目標を掲げています。
健全な生態系については、生物多様性に焦点を当てたロードマップになっています。生態系は、気候変動と相互に影響する問題で、エネルギー転換と合わせて考えながら目標を設定しました。
気候変動はグローバルな問題ですが、生態系は地域ごとに課題が異なり、評価すべきポイントも変わる点には注意が必要です。生態系に関する議論はまだ成熟しきっていませんが、7〜8年前の気候変動に関する議論と似たような段階にあると考えています。
社会における平等性の向上については、昨年末に新たにロードマップを発表しました。多様性は、文化的背景の違いから目指すべき姿が国や地域ごとに異なる部分もあります。そのため、根拠を重視し「なぜそれが必要なのか」を示すことを意識しました。社会における平等性の向上は、他の2つの分野よりも複雑で、達成まで時間のかかる課題だと考えています。
スチュワードシップ活動の事例
――どのようなスチュワードシップ活動を実践されていますか? 象徴的な事例を教えてください。
「3つのE」の実現にスチュワードシップ活動は欠かせないという考えのもと、さまざまな取り組みを展開しています。
健全な生態系での興味深いものとして、当社のエンゲージメントによりカブトガニ保護が促進された事例を説明します。カブトガニの血液は、医療機器に付着した汚染を検出する試薬に用いられています。この試薬は、天然資源だとカブトガニの血液からしか製造できません。しかし、最近の調査で明らかになっているように、カブトガニは絶滅の危機に瀕しており、製薬業界全体でのリスクにつながる恐れがあると判断しました。
そこで当社では、他社に先駆けて、カブトガニに代わる合成代替品の使用を促すエンゲージメントを開始。当社のエンゲージメントにより、25%の製薬企業からカブトガニを乱獲しないことや代替品を使用するなどのコミットメントを引き出すことができました。
――その他にはどんな事例がありますか?
共同エンゲージメントも、代表的な事例として挙げられます。エネルギー転換では温室効果ガス排出量削減の効果的な推進を目指す「Climate Action 100+」、健全な生態系では自然の保護や回復などに取り組む「Nature Action 100」といったイニシアティブで主導的な役割を果たしています。
社会における平等性の向上では、取締役のダイバーシティに関する取り組みが代表的な事例の一つです。欧米では40%、アジアでは20%の女性の取締役比率を求めており(2025年3月時点)、基準に達しない場合には全員に反対票を投じる議決権を行使しています。この比率はかなり高い基準になっています。
共同エンゲージメントの意義と課題
――欧米では共同エンゲージメントがどの程度スタンダードになっているのでしょうか?また、投資家や企業にどのような影響をもたらしていますか?
欧州ではスタンダードな方法になっています。米国でも同様でしたが、最近は一部の企業が共同エンゲージメントの枠組みから離脱するなど少し変化も見られます。とはいえ、気候変動や生物多様性といった一社では対応できない体系的なリスクに向けた取り組みには、共同エンゲージメントが重要だと私たちは考えています。
共同エンゲージメントのメリットはいくつもありますが、例えば、企業への期待値が平準化され、投資家の判断基準が明確になる点が挙げられるでしょう。これには、企業側にとっても達成すべき目標を設定しやすい、というメリットもあります。
さらに、複数の投資家が共同しているので、効率性も高いです。一つのテーマに対して何度も個別にミーティングを行う必要がなくなります。ただし、投資家同士の考えが異なる場合には追加でフォローしなければなりません。
――日本では、昨年アセットオーナープリンシプルが設定されたことなどを受け、年金・機関投資家のスチュワードシップ活動に対する期待も高まっています。
ICGNの議論を経て、日本の状況はポジティブだと認識しています。資本効率の改善といったガバナンス面などで進展が見られます。
しかし、課題もあります。取締役の女性比率の改善、ビジネスとの関係性が乏しい株式持ち合いの解消、情報開示のスピードを高めることです。最後の情報開示については、欧州ではアニュアルレポートが株主総会前に公表されるのに対し、日本では総会後に公表されている、といった課題があります。こうした点を解消しながら、日本市場がより一層発展していくことを期待しています。
プロフィール
BNPパリバ・アセットマネジメント
グローバル・ヘッド・オブ・スチュワードシップ&議決権行使
マイケル・ハースコビッチ 氏(Michael Herskovich)
2008年にサステナビリティ・センターのスチュワードシップおよび議決権行使の責任者として、BNPパリバ・アセットマネジメントに入社して以来、議決権行使、エンゲージメント、コーポレートガバナンス分析を含むスチュワードシップポリシーを担当。当社のグローバル・サステナブル・ポリシーの策定と実施を行い、ESGリサーチと統合の推進に貢献。国際コーポレートガバナンスネットワーク(ICGN)のメンバー。
フランス資産運用協会(AFG)のコーポレートガバナンス委員会及び、機関投資家評議会(CII)の国際コーポレートガバナンス委員会の委員長。ICGNのベストプラクティス原則(BPP)監視委員会及び、株主権利委員会および投資家団体のグローバルネットワーク「GNIA」委員会の委員。フランス資産運用会社協会(AFG)の責任投資委員会、オランダ機関投資家団体Eumedionの投資委員会及び、フランス「Grand prix jury of the general meetings」などの委員。
同社入社前は、2006年から2008年まで弁護士として勤務し、パリの「Fonds de Reserve des Retraites」(フランス年金基金)の議決権行使を担当。パリ=サクレ―大学(フランス)を卒業し、2008年に会社法およびビジネス法の修士号を取得。